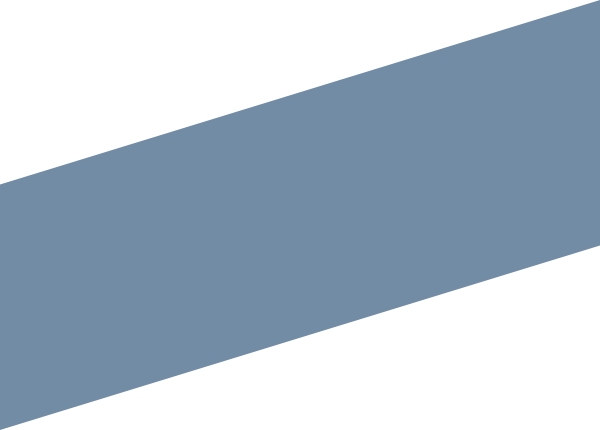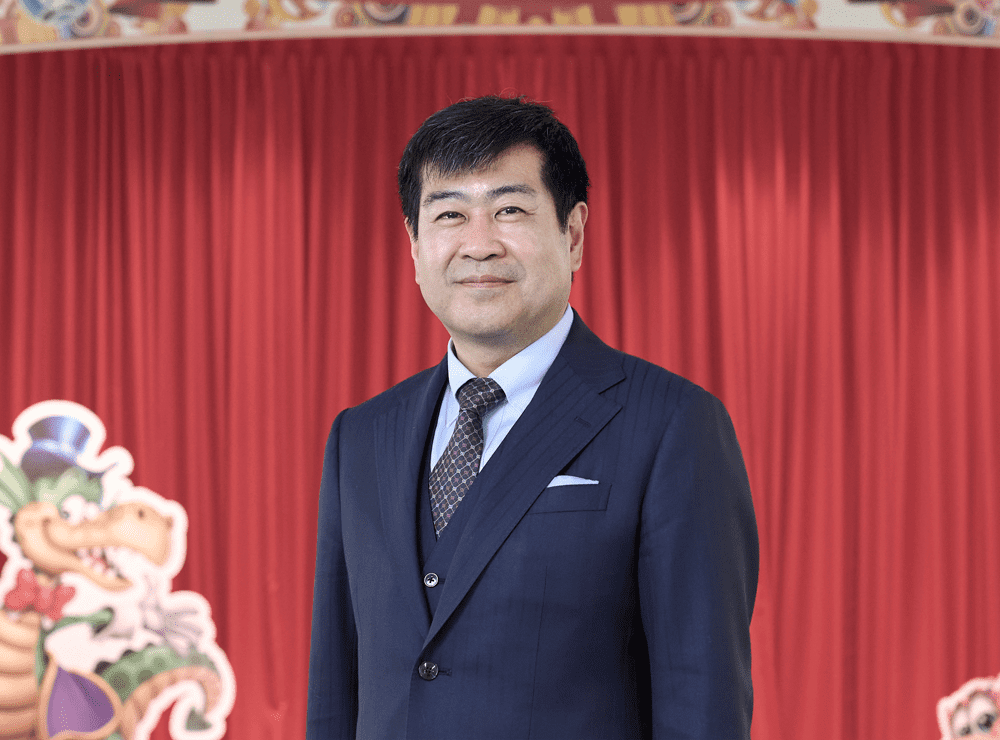親鸞の言葉で、人生観が一変。
物事をやり抜く姿勢に。
寄神社長は、どのような子ども時代を過ごされましたか?
私は京都出身で、陶芸家の両親の息子として育ちました。そのため、幼い頃は「自分のやりたいことは、どんどんやりなさい」という、右脳を軸とした育てられ方だったと記憶しています。小学校では、絵画で小さな賞をいただいたり、校長先生が話す登壇の横に置いてある花瓶が、私の陶芸作品だったりしました。
ただ、年を重ねる中で「作品を少しでも良くしてやろう!」と力が入り出すと、逆に上手くいかなくなって、小学生ながら「芸術の才能はないな…」と見切りました。当時の私は、勉強も部活もある程度卒なくこなしてしまう。だから、「まぁ、この程度で良いか」という感じで大して努力もせずに、小中高と過ごしてきました。ところが、大学で転機が訪れます。
大学時代に訪れたターニングポイントとは?
私は、地元京都で歴史のある仏教系の大学に入って、サークルを立ち上げたりしながら、楽しくキャンパスライフを送っていましたが、講義で学んだ浄土真宗の親鸞の教えが、私の人生観を大きく変えることになります。
教授が解釈する親鸞の教えは、こういった内容でした。「人の死に顔は、自分で操れない。死に顔には、その人の生きてきた人生が、現れる。一生懸命生きてきた人は、晴れやかでいい死に顔をしている」と。この教えを聞いて、「今までの人生、自分はどうだったのか。自分が満足出来るほど何かに一生懸命、取り組んだことがあったのか?」と振り返りました。それなりにはやってきたけど、突き抜けて何か努力はして来なかった…そう感じた私は、この講義をきっかけに大学を辞めました。そして、一からリセットして勉強し直して、経済界でも著名な卒業生の多い大学に入り経済学を一から学ぶことにしました。
大学時代の私は、ランドクルーザーという車が好きになり、全国的なクラブに参加していました。私は中古の安いランドクルーザーに乗っていましたが、新車のランドクルーザーはそれなりに高価な車なので、クラブメンバーは中小企業の社長さんたちが多くて、学生は私くらい(笑)。そういう方々と同じ車好きという立場で世代や地位を越えた人付き合いを学べたおかげで、“相手の懐に入って、自分の考えを打ち出す”という、私のスタイルが出来上がりました。